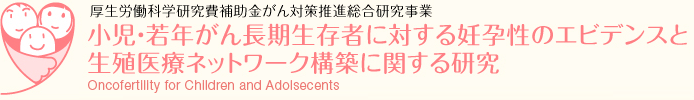他領域での取り組み
若年乳がん
若年乳がん(若年性乳がん)とは、若年で発症する乳がんで、「若年」を規定する明確な定義はありませんが、一般的に35歳未満または40歳未満とされます。乳がんの好発年齢は40歳代後半以降で、2019年の全国がん登録の推計では40歳未満の乳がん患者(上皮内がんを含む)は全体の約4%でした。
乳がんの予後には、がんの広がり(しこりの大きさ、腋窩リンパ節転移の状況、遠隔転移の有無)、がん細胞の形態(組織型)、がんの生物学的な性質が影響を与えます。乳がんの性質は、病理検査で、エストロゲン受容体(ER)、プロゲステロン受容体(PgR)、HER2、Ki67などのたんぱく質が、がん細胞にどれくらい発現しているかということで評価します。こうしたタンパクの発現状況で、ルミナルA型(ホルモン受容体陽性、HER2陰性、Ki67低値)、ルミナルB(HER2陽性)型(ホルモン受容体陽性、HER2陽性)、ルミナルB(HER2陰性)型(ホルモン受容体陽性、HER2陰性、Ki67高値)、HER2陽性型(ホルモン受容体陰性、HER2陽性)、トリプルネガティブ型(ER、PgR、HER2のいずれも陰性)に分類しています(サブタイプ)。
乳がんの手術の前後に、再発リスクを下げるために、抗がん剤治療を行うことがあります。術前に行う抗がん剤の治療を術前薬物療法、術後に行われる抗がん剤の治療を術後薬物療法といいます。術前化学療法は、ステージが高い場合の選択肢です。抗がん剤治療は、化学療法、ホルモン療法、分子標的療法に分類され、がんの広がり、がんの組織型、がんのサブタイプ等から推定される再発リスクの大きさや、各種抗がん剤により期待できる効果、抗がん剤による副作用と効果のバランスを考えて選択します。現在、標準的な抗がん剤治療として、アントラサイクリン系薬剤とタキサン系を中心とした化学療法、ホルモン受容体陽性の場合には5-10年間のホルモン療法が、HER2陽性の場合には1年間のHER2を標的とした分子標的療法の投与が推奨されています。近年では、再発リスクが高い場合、それらに加えて、がんのサブタイプに応じて、CDK4/6阻害薬、PARP阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬といった新しい分子標的薬を加えることもあります。
挙児希望の乳がん患者さんにとっては、化学療法による卵巣機能障害や長期のホルモン療法が問題となります。また新しい分子標的薬については卵巣機能など妊娠する力への影響が十分にわかっていないものもあります。乳がんの抗がん剤治療が妊娠・出産にもたらす問題については、医療従事者向けに作成された「乳がん患者の妊娠出産と生殖医療に関する診療ガイドライン2021年版(日本がん・生殖医療学会編)」も公開されていますので、ぜひご覧ください。
またこのホームページの中では、「乳がん治療にあたり 将来の出産を希望の患者さんへ」という小冊子を自由にダウンロードできるようにしていますのでご活用ください。
子宮頸がん
上皮内癌や微小浸潤癌(子宮頸がんIA期)には、診断と治療を兼ねて子宮頸部円錐切除を行います。腟から挿入した器具で、頸部を円錐状に切除して顕微鏡で観察します。細胞診や狙い生検で上記の病変が疑われたときは、頸部円錐切除を行い、その摘出標本の病理検査で病変の程度、切除断端の状態を評価し、経過観察とするか追加治療が必要かを判断します。この手術をおこなうことにより、妊娠・出産への影響を最小限にします。
小さな浸潤癌(子宮頸がんIB期、腫瘍径2cm以下)には、広汎子宮頸部全摘術が行われています。子宮頸部を広く切除して、温存した子宮体部と腟を縫合する方法です。子宮までのアプローチに、腟式・開腹・腹腔鏡下の方法がありますが、腟式術式の場合は妊娠・出産例が多く報告されています。ただしリンパ節転移があると予後不良ですので、本術式の適応とはなりません。一般に2cm以下の頸がんでは7%にリンパ節転移があります。もし術中にリンパ節転移が判明したら術式を変更します。
(文責:加藤友康)
子宮体がん
早期の子宮体がんの場合には、高用量の黄体ホルモン服用と子宮内膜全面掻爬(そうは)を組み合わせて、体がんの消失を狙います。適用の条件として、生検にて高分化型類内膜腺癌であること、MRIで筋層浸潤が指摘されていないこと、標準治療として確立していないことに十分理解していることの3条件を満たす必要があります。治療は原則6ヶ月間行います。厳重な経過観察を行い、癌細胞が消えない場合には子宮摘出に切り替えなければなりません。最近の本邦の報告をまとめると、126例中89例(71%)で癌が消失。そのうちの73例中25例(34%)が妊娠に至りましたが、48%に再発が認められています。このように確立した治療ではないので慎重な経過観察が必要です。
(文責:加藤友康)
卵巣がん
卵巣がんは大きく分けて、胚細胞性腫瘍、性索間質腫瘍、上皮性腫瘍、に分けられます。胚細胞性腫瘍、性索間質腫瘍で妊孕能温存を希望する場合には患側附属器切除を行い、健側の附属器(卵巣・卵管)を温存します。病理結果と進行期から、進行例では術後に化学療法を追加します。
上皮性腫瘍は、さらに悪性腫瘍と境界悪性腫瘍に分類されます。それぞれの組織型は漿液性、粘液性、類内膜、明細胞の4つに定義されます。「卵巣がん治療ガイドライン2015年度版」では、妊孕性温存手術(患側の附属器のみ切除)を行うことのできる臨床病理学的な必要条件として、「明細胞腺癌以外のIA期でGrade 1,2」とされています。「明細胞腺癌のIA期」と「明細胞腺癌以外のIC期でGrade 1,2」は妊孕性温存が考慮されるとしています。この2群には、抗がん剤治療を追加する臨床試験が行われています。「明細胞腺癌のIC期」は再発例が多く、妊孕性温存の適応外とされています。迅速病理検査でこの適応を決定するのは難しく、永久標本による診断を待つ必要があり、手術が二期的になることも避けられません。
(参考)
組織学的異型度(漿液性、粘液性、類内膜腺癌)
G1: 充実性に増殖している部分が腫瘍全体の5%未満のもの
G2: 充実性に増殖している部分が腫瘍全体の5~50%を占めるもの
G3: 充実性に増殖している部分が腫瘍全体の50%を越えるもの
進行期
I期 卵巣内限局発育
IA期 腫瘍が一側の卵巣に限局しているもの(癌性腹水なし、卵巣被膜表面への浸潤や被膜破綻なし)
(文責:加藤友康)